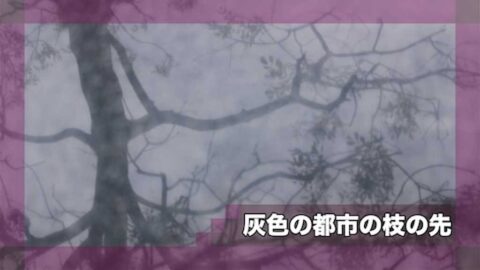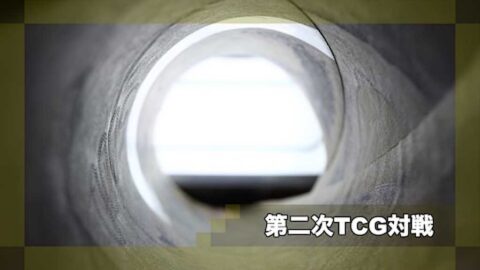透明な朝、転がる何か。
瑠璃色の空は、まだ目を覚ましたばかりだった。夜の余韻がわずかに残る空気はひんやりとしていて、肺の奥にすっと沁みる。公園のベンチに腰を下ろした津田悠馬は、小さく息を吐いて空を仰いだ。
街はまだ静かだった。通勤ラッシュには少し早く、近所のコンビニに向かう人が数人いるだけ。カラスが電線にとまって、目だけで彼をじっと見ている。彼はそんな視線にも構わず、そっとポケットに手を入れた。
取り出したのは、小さなサイコロ。六面体のその一つ一つが、微妙に色を変えている。角度によっては空の青を映し、朝の光を受けて虹のような輝きを放つ。まるでこの地球の縮図のようだった。
彼はそれを指先で軽く弾いた。コトン、という控えめな音とともに、サイコロはベンチの木の上を転がり、止まった。
出た目は『1』
「また、か…。」彼は少しだけ眉を動かしてつぶやいた。
ここ数日、同じ目ばかりが続いていた。完全な偶然かもしれない。でも、彼はそこに何かを感じてしまう。
運命の偏り? 神のメッセージ? あるいは、自分の思考の癖が引き寄せた象徴なのか?
サイコロを拾い上げるとき、彼の手がわずかに震えた。けれど、それは冷たさのせいではなかった。
この世界に本当に「偶然」なんて存在するのだろうか?そう問いかける彼自身の声が、どこか深い場所でこだましていた。
「確率は、公平なふりをして不平等だ」
それが彼の信条だった。
彼は大学で社会構造を研究していたが、それは同時に人間の見えない選択について探る旅でもあった。
人は自由に選択していると思い込んでいるけれど、実際は生まれた場所、受けた教育、育った家庭――、すべてが背景として配置されており、選択とは言えない配置された結果に過ぎないのではないか。
まるで誰かがサイコロを振り続け、出た目によって人生が定まっていく。そのサイコロを、自分で振っていると思い込んでいるだけかもしれないのだ。
「…でも、たとえそうでも」
彼はサイコロを強く握った。ガラス越しに朝の光が指の隙間から漏れ、掌の中で微かに揺れているように見えた。
「僕はこの手で振る。この目で見て、この意味を僕が決める」
遠くで自転車のベルが鳴った。小学生たちの笑い声が聞こえてくる。新しい朝が、今日という日を始めようとしていた。
サイコロを再びポケットにしまい、悠馬はベンチから立ち上がった。一歩踏み出すたびに、足元の土がわずかに鳴る。世界がまだ完全に目覚める前の、この静かな時間こそが、彼にとっての自由だった。
そして彼は、誰にも知られないまま、小さな挑戦を始めていた。
それは、この世界が本当に偶然でできているのかを、自分の手で確かめるという、静かで壮大な挑戦だった。
歴史は誰のサイコロで決まったのか
その日、大学の研究棟は冷たく乾いた静けさに包まれていた。廊下に差し込む光は白く、どこか人工的で、まるでここが現実から切り離された実験室のように思える。人の姿はまばらで、印刷機の駆動音とパソコンのキーを叩く音が遠くで反響している。
悠馬は、ゼミ室の片隅でノートパソコンを開きながら、ある論文の一節を何度も読み返していた。
「歴史的転換点の多くは、制度設計や指導者の意思決定ではなく、偶然の積み重ねとして説明されうる」
それはとある社会史学者の主張だった。初めて読んだとき、彼の心は妙に落ち着いた。それまで「なぜこの世界はこうなっているのか」という問いが彼の中で常に燻っていたが、この一文がその煙に一本の光を通したような気がした。
だがその日は、いつも以上に気分がざらついていた。目を閉じると、昨日見たニュースの映像が浮かぶ。戦争、経済危機、自然災害。そして、誰かが失言したとか、誰かが失脚したとか。
「本当に、これ全部が最善の判断の結果なのか?」そう問いかける声が、また彼の中で疼く。
その時、背後から聞き慣れた声がした。
「また難しい顔してるな、津田くん」
振り返ると、ゼミ指導者の村崎教授が、書類の束を小脇に抱えて立っていた。歳の割にラフな格好で、灰色のセーターの肘はすっかり擦り切れている。
「先生。偶然って、どこまで許されると思いますか?」
「なんだ急に」
「人類の歴史が、もし全部誰かの振ったサイコロの目で決まっていたとしたら、僕らの倫理って、ただの後づけじゃないですか?」
村崎教授は少しだけ眉を上げて、手にしていた書類を机に置いた。
「また君らしい問いだな」
彼はコーヒーカップに口をつけてから、ゆっくりと話し始めた。
「歴史には選択の痕跡が確かにある。けれどそれを決定づけた要素は、常に混ざり合っている。意志と偶然、利害と感情、善意と誤解……どれか一つだけでは動かないんだよ」
「でも、じゃああの戦争も、あの革命も、全部『たまたま』だった可能性があるってことですか?」
「その『たまたま』を構成する因果のネットワークを、君はどう捉える?」
教授の問いに、悠馬は言葉を詰まらせた。
「君は社会を、サイコロのように見ている。でも、面白いのは――、サイコロを振っているのが誰か一人ではなく、みんなだということなんだ」
教授は静かに笑った。
「私たちは自分で振っているようで、実は誰かの振った揺れに巻き込まれてる。そして、私たちの振った目もまた、誰かに影響を与えてる。そうやって歴史は、まるで大きな連鎖反応みたいに動いていくんだよ」
その言葉は、悠馬の中で少しずつ形を成し始めた。確率という無慈悲なシステムの中にも、連なりがある――。秩序を紡ぐ無秩序が、社会という形をとって姿を現しているのかもしれない。
彼はふと、自分のノートの余白に書き残していたフレーズを思い出した。
「選ばれた結果ではなく、出た目に意味を与えること。それが僕たちの歴史意識の根っこだ。」
彼はその行に線を引いた。
そして思った。歴史は誰かの一つのサイコロで決まったのではなく、誰かたちの無数のサイコロで組み立てられた軌跡なのだと。
その夜、彼は自室に戻って再びサイコロを手にした。蛍光灯の下で見るガラスのサイコロは、朝とは違い、冷たく鋭い輝きを放っていた。
振ってみると、『4』が出た。中間的な数字。妥協、調整、そして均衡。
「…ちょうどいいかもな」
彼はそう呟いて、窓の外に広がる夜の都市を見つめた。そこには、無数のサイコロが、今も誰かの掌の中で転がり続けている気がした。
無秩序に生きるという自然性
休日の午後、津田悠馬は町の外れにある川辺の遊歩道を歩いていた。
研究室から離れ、スマートフォンの通知も切って、ただ風の音と足音だけが彼の耳に届く。こうして一人になると、自分の思考と素直に向き合える気がする。
河原には春の陽射しが降り注ぎ、まだ若い緑がまぶしく揺れていた。遠くの橋を電車が通りすぎ、軽い地鳴りのような振動が足元に伝わってくる。
悠馬は川沿いのベンチに腰を下ろし、手のひらの中の小さなサイコロを見つめた。
「人間って、本当は動物なんだよな」
そう口に出すと、自分の声が少しだけ風に溶けていくのが分かった。
人間は理性を持ち、文化を作り、秩序を好む。
けれどもその根底にあるのは、生物としての衝動、欲求、不確定な反応――。つまり、予測不能な存在。それはまるで、どこに転がるか分からないサイコロのようだ。
ふと視線を足元に移すと、小さなアリたちが列を成して歩いていた。行き先など分かっているのかと問いたくなるほどの自由さで、それでいて確かに目的を持っているようにも見える。
「どこまでが本能で、どこからが意識なんだろうな」
彼はしゃがみ込み、しばらくアリの動きを見つめていた。完全な秩序のように見えて、時折列を外れるアリがいる。けれど、それもまた全体の流れに混ざっていく。逸脱すらも自然の一部として吸収されていくのだ。
「社会って、もっとこうあるべきじゃないのかな……」
人間社会は、逸脱を誤りと捉える。無秩序を排除すべきものとみなす。
けれど、自然は違う。そこには管理する誰かはいないのに、調和している。あるがままを許容して、それぞれが役割を果たしている。魚は流れに従い、鳥は風に乗る。そこには「計画」も「成功」も「正義」すら存在しない。ただあるということ、それだけ。
悠馬はポケットからサイコロを取り出し、土の上にそっと転がした。
『2』
「弱さ」とか「脇役」とか、そんなイメージが浮かんだ。だが、それもまた大事な一面。6面のうちのひとつに過ぎない。全ての目があって、サイコロはサイコロとして存在している。
彼はそれを拾い上げ、手のひらの中でゆっくり転がした。
「無秩序であることを怖がるから、人間は不自由になるのかもな」
自然は完璧を目指さない。ただ生きて、ただ変化する。それは不安定に見えるが、同時に最も確かなリズムでもある。
悠馬の背中に、そよ風が吹いた。その風は、どこか懐かしく、森の記憶を含んでいるようだった。
彼は立ち上がり、歩き出した。舗装された遊歩道から外れ、少しだけ草の深いところへ踏み出してみる。足元は不安定だが、土の感触が直に伝わってくる。その不確かさが、むしろ今の自分には心地よかった。
「秩序の隙間に、本当の自由があるのかもしれないな」
空を見上げると、雲ひとつない瑠璃色の青空が広がっていた。その広さに、何かを委ねたくなる衝動が込み上げる。
人間もまた、森の木や川の魚と同じくどこへ行くのか分からない存在であっていい。意味を探すよりも、まず存在することに耳をすませば、それだけで十分なのかもしれない。
彼は最後にもう一度サイコロを握りしめ、そっとポケットに戻した。
無秩序。それは怖い言葉じゃない。それは生きているということと、同じ意味なのだ。
運試しとしての今日
朝、目覚まし時計が鳴る直前に目が覚めた。窓の隙間から差し込む光が、カーテンの端を瑠璃色に染めていた。
悠馬は時計を見て、こう思った。
「これは…運がいいのか? それとも、ただの偶然か?」
彼にとって今日というものは、毎朝一度だけ与えられる運試しのようなものだった。
一日をどう過ごすかではなく、「どんな目が出るか」。その感覚は、決して投げやりではない。むしろ、自分のコントロールを越えた現象に対する謙虚な観察姿勢だった。
カーテンを開けると、雲ひとつない空が広がっていた。
ふと、彼はある決意をする。
「今日はサイコロを振るように、生きてみようか」
そう言って、机の引き出しからノートを取り出し、表紙に小さな文字で書いた。
『本日の出目:□』
そこに出た目によって、今日一日の過ごし方を決めてみよう――。彼なりの、偶然との対話だった。
朝食をとり、身支度を済ませると、サイコロをそっと掌にのせた。彼は少し緊張した面持ちでそれを転がす。
コトン。
出た目は『5』
彼は小さくうなずいた。5は「変化」「少し大胆に」「寄り道を許す」という、自分なりの意味づけをしていた。
「なるほど、今日は寄り道の日か」
普段なら大学に直行するが、今日は少しだけルートを変えることにした。ふと思いついて、昔よく通っていた小さな商店街を回ってみる。かつての文具店は閉店していて、かわりに雑貨屋になっていた。
道端のコーヒースタンドに立ち寄ると、初老の男性が一人で切り盛りしていた。
「朝からいい顔してるね、学生さん」と声をかけられる。
「運が良かったんです。サイコロの出目が良かったんで」
「ほう、サイコロで一日を決めてるのか。面白いねえ。でもまあ、運を信じるってことは、何かに身をゆだねるってことでもあるからなあ。いざというとき、意外と強くなれるよ」
コーヒーを受け取って別れた後、悠馬は思わず微笑んだ。
「そうか、身をゆだねるって、逃げることじゃなくて、委ねる勇気なんだな」
その言葉が胸の中にすっと染み込んできた。
昼、大学に着くと、ゼミ仲間の一人が話しかけてきた。
「なあ、急なんだけど、今夜ちょっとした勉強会やるんだ。よかったら来ない?」
本来なら、人付き合いの濃い時間は避けたがる性格だ。けれど今日は5の日。変化と寄り道を意味する日だ。だから彼は、少しだけ迷ってからうなずいた。
「うん、行ってみるよ」
夜、勉強会では思いがけず、環境倫理学を専攻する他学部の『高梨つかさ』と話す機会があった。自然との共生や、非人間中心的な視点について熱く語る彼女の姿に、悠馬はどこか親近感を覚えた。
思えば自分もまた、秩序から離れたところに本質があるのではないかと考えていた。
会の終わりに、彼女はこう言った。
「でもね、自然って正解がないでしょ? それが怖くもあるし、救いでもあるのよね」
「まさに、サイコロと同じですね」
悠馬がそう答えると、彼女は不思議そうに笑った。
帰り道、夜の街を歩きながら、悠馬はふとポケットに手を入れ、サイコロを握った。少し冷たくなったその感触は、なぜか心地よかった。
「今日の5は、予想以上に豊かだったな」
彼は歩道橋の上で立ち止まり、下を走る車のライトを見下ろした。まるでそれぞれが別々の方向に転がっていくサイコロの目のようだった。
「偶然を偶然のまま受け入れることで、僕は少しだけ自由になれているのかもしれない」
そう呟いたとき、胸の奥で静かに何かが確かに「腑に落ちた」気がした。
意味を与えるのは、私たち自身
「意味なんて、最初からどこにもなかったのかもしれない」
そう思う瞬間が、誰にでもあるだろう。
深夜の帰り道、バス停で誰もいない道を眺めながら、悠馬もまたそう感じていた。
木々が揺れる音、信号機の規則的な点滅、遠くで聞こえる踏切の音――、すべてが、ただそこに起きているだけの事象に思えた。
けれど彼は、ふとしたことを思い出した。
小学生の頃、よく拾った石に名前をつけていた。「旅石」「風石」「宇宙石」…その石自体には何の意味もなかったはずだ。でも自分が名前を与えると、たちまちそれは何か特別なものになった。
あの感覚を、今も取り戻せるだろうか。
ある日のゼミで、村崎教授が言った。「人間は、意味を与える動物です。神話をつくり、制度を設計し、物語を生きる。けれど、世界は本質的には沈黙している。意味を語ってくれはしない。だからこそ、私たちが意味づけしなければならない」
悠馬は、その言葉をメモ帳に書きとめたあと、しばらくそれを眺めていた。
世界が沈黙しているからこそ、僕たちは語らなければならない。それは、ある種の「責任」かもしれないと思った。
ゼミ帰り、彼は勉強会で知り合った環境倫理学の高梨とカフェで話す機会があった。
「ねぇ、悠馬くん。意味って、最初からあって見つけるものだと思ってた?それとも、後からつくるもの?」
「昔は前者だったけど、今は……たぶん、後者かな。でも後からつくったって自覚があると、どこかで自信が揺らぐこともある」
高梨はカップを置いて、静かに言った。
「それでも、選ぶことをやめないってすごいことよ。選ぶって、世界に自分の手形を押すようなものだから」
悠馬は、はっとしたように言葉を飲み込んだ。
彼女の言葉は、意味は自分で与えるという発想を、ただの自己満足ではなく、他者や世界との関係の中での表明として、捉えなおさせてくれた。
その晩、帰宅してから彼は自分のノートを開いた。最初のページに書いた「意味なんて、ないのかもしれない」という言葉の下に、新たな一文を綴る。
それでも、意味を与えることを選びたい。それは、今日という日をただの一日で終わらせないための、僕なりの祈りだ。
意味は与えられるものでも、誰かに保証されるものでもない。けれど、それでもなお「自分が意味を与えること」ができるという事実は、何よりも強い。
風に揺れるカーテンの向こうで、街灯の光が揺れていた。その光景も、彼が「美しい」と思えば、きっと意味を持つ。
「意味を与えるのは、世界じゃない。――僕たち自身なんだ」
心の奥に静かに灯ったこの思いを、彼はそっと胸にしまった。
世界は常に編集可能である
ある冬の終わり、津田悠馬はひとりで八戸を訪れていた。列車に乗るのも、宿を取るのも、すべて「予約なし」で来た小さな旅。偶然に導かれた旅だったが、それでいて妙に納得のいく選択だった。
朝の漁港。温かい磯汁と、湯気を上げる朝日。人々の声。並ぶ野菜。浜風に吹かれながら、彼はふと思った。
こんなにも雑多で、散らかったこの世界が、どうしてこんなに美しく見えるのか。
帰り道の列車の中で、悠馬はノートを開いた。そこには、かつて書いた断片的な思索の言葉が並んでいた。
「無秩序に転がる朝」「歴史は誰のサイコロで決まったのか」「無秩序に生きるという自然性」「運試しとしての今日」「意味を与えるのは、私たち自身」
そのすべてが、まるでひとつの「編集された書物」のように、静かに並んでいた。
思えば、彼が見てきたのは完成された真理ではなく、書きかけの下書きのような世界だった。そこに記される言葉や構図は、見る人の視点によっていくらでも変わりうる。大事なのは、どこをカットして、どこに句読点を打つかを決める主体の在り方だ。
世界は原稿用紙じゃない。けれど、僕たちはその余白に自由に言葉を綴ることができる。
夜、東京のアパートに戻った悠馬は、机に向かって文章を書いていた。就職活動の一環で始めたポートフォリオには、「自分が見てきた世界」について書く欄がある。
彼は迷わずこう綴った。
『世界は、編集可能である。風景も、過去も、人との出会いも、すべてはどのように語るかによって色を変える。偶然や無意味を恐れるのではなく、それすらも語りの一部にしていくこと。それが、私たちが生きるということなのだと思う。』
書き終えると、彼は画面を閉じ、窓を開けた。夜風が、春の匂いを運んできた。
翌朝、悠馬は目覚まし時計より早く起きた。透明な朝。鳥の声。少し早めに家を出ると、まだ人通りの少ない道にやわらかい光が差し込んでいた。
道端でふと足を止める。昨日の夜に降った雨のしずくが、葉の先で光っていた。
その一瞬にカメラを向け、シャッターを切った。
この瞬間に意味があるかどうかはわからない。でも、僕が美しいと思ったなら、それだけでいい。
今日のサイコロの出目は『6』だった。6は「思考」「再構築」「振り返り」と意味付けている。
彼は再び歩き出す。『編集』は終わらない。むしろ今が、その始まりの第一章なのかもしれない。
HiStory[単行本]
HiStory「シーズン1」から「シーズン4」までのお話を収録した単行本を注文できます。
完全オリジナル、完全受注生産。
ここでしか入手できない創作小説。旅のお供に持って行ったり、夜の静かな自分時間にお楽しみいただける一冊に仕上げました。
紙の本だからこその永久保存版として、ぜひあなたのライブラリーに追加してください。


![HiStory[単行本]](https://hilens.net/wp-content/uploads/2025/07/historybook_artwork.jpg)