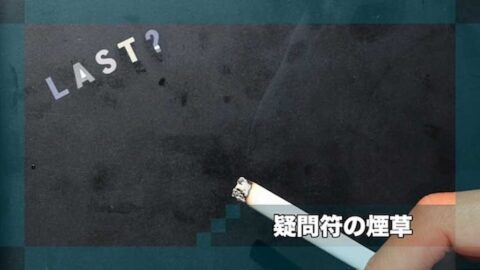酸性雨が止んだのは、3日前のことだった。
それでも空は、変わらずに灰色だ。低く垂れ込めた雲の下を、俺はフードの奥で息を潜めるように歩いていた。
「おじいちゃん、昔は空が青かったって本当?」
そう聞いたのは、養女のミナだった。10歳。俺がかつて設計していた『便利な都市』では、子どもたちは空の色さえ知らずに育っている。
「本当さ。でも、長くはなかった。」
答えるたびに、心がちくりと痛む。この街にはもう、緑はない。土に触れた記憶も、草の匂いも、人工フィルターの中で作られた「再現データ」でしか知らない世代が大半になった。
街の壁には、かつて自分がデザインに関わったポスターが残っていた。
『持続可能な未来へ──グリーン・スマート都市構想』
赤錆に侵食され、今や皮肉にしか見えないその言葉を、通りすがりの誰も見ようとしない。この都市はもう終わったものとして機能している。ただ壊れずに、音を立てずに、朽ちていく。
ミナが不意に言った。
「雨って、なんでしょっぱいの?」
それは……たぶん、塩?いや、もしかしたら、誰かの涙なのかもしれないな。世界が自分で壊したことに、誰も気づかないまま、それでも便利さを追い続けた人類の涙だ。
「おじいちゃんも、その昔、車をいっぱいつくった?」
「……ああ。」
俺の手は、あの時のCAD操作をまだ覚えている。環境効率という名目のもと、数千台のスマート車両を設計した。だがそれが、結局はさらにCO2を増やし、都市の空気を汚したのだ。
便利という言葉はいつから麻薬になったのだろう。人々は新機能に夢中になり、最新技術に酔いしれていた。だが誰も、『その先』の問いを持とうとしなかった。
「じゃあ、未来はどうなるの?」
ミナが、真っ直ぐに俺を見る。この街の空が灰色でも、彼女の瞳は澄んでいる。
「未来は……まだ、決まっていない。」
嘘でもなく、本当でもない。けれど、そう言うしかなかった。
俺が最後に設計したもの。それは車でも都市でもなかった。それは「哲学」だった。
『人類は、自然に勝てなかった。だが、共に在ることはできたはずだ。』
それを、今さら言葉にしても遅いかもしれない。けれど、子どもたちには渡したい。
ミナが小さな手で空を指さす。
「あれ、ちょっとだけ……青い?」
見上げた空の端、確かに、雲の切れ間から微かに光が覗いていた。青というよりは、白に近い。それでも、何かが変わる気がした。
この都市に、最後のデザインがあるとすれば、それは『誰かが後悔を抱いて歩き続ける姿』だ。もう、便利であることが目的ではない。生き延びるための、選択を問う旅が、ようやく始まるのかもしれない。
俺はミナの手を握った。
「歩こう。風のあるほうへ。」
灰色の雨は止み、世界はまだ、終わっていなかった。
回想『グリーン・スマート都市構想』
「おめでとうございます。あなたの都市構想が、最終採択されました。」
そのメールが届いたとき、俺は息を呑んだ。この10年間、研究所で積み上げた構想が、ついに現実になる──そんな興奮と達成感が一気に体を駆け巡った。
プロジェクト名は《GSP(Green Smart Planetary City)》。自動運転とスマートエネルギーの結節点に位置づけられた、未来型の都市開発モデルだった。
キーワードは「持続可能」と「効率化」。温室効果ガスを削減するためのAI交通管理、再生エネルギーによる都市インフラ、すべてのデータをリアルタイムで解析するセンサー網。この都市では、ゴミでさえもデータとして分類され、すべてが計算された最適解として循環する──はずだった。
それが理想だった。
「便利と安全、それが都市設計の使命です。」
プレゼンでそう語ったとき、聴衆の目は輝いていた。省エネ住宅群、立体交差で渋滞ゼロの交通網、中央管理センターによる都市の自己修復機能。そのビジュアルには緑が溢れ、空はどこまでも青かった。都市は人間の叡智の結晶だと、誰もが信じて疑わなかった。
ただ一人を除いて。
それは、同僚の環境研究者、結城だった。
「お前の都市は綺麗すぎる。自然が一切入っていない。」
「緑化計画はある。AIによる植生管理も──」
「それは自然じゃない。ただの『景観設計』だ。雨の音も、風の匂いも、人間が感じる異物が排除されすぎてる。」
彼女の言葉は、どこか反抗的で、同時にどこか優しかった。
「この都市に生まれる子どもたちは、本来の自然を一切知らずに育つ。その意味を、考えたことあるか?」
そのときの俺は、構想を否定される悔しさのあまり、聞く耳を持たなかった。
やがて都市は実際に稼働を始めた。光の整った街路、CO2排出を数値化して最小化する運転制御、自動浄水システム。一見、すべてが完璧だった。
だが、1年後。想定外の豪雨により、センサー網は誤作動を起こし、処理待ちの汚水が川へ流れ込んだ。翌年、海洋からマイクロプラスチックが検出され、生態系の一部が崩壊した。
それでも都市は稼働を止めなかった。なぜなら、最優先されたのは人間の利便性だったからだ。
街の空気は静かだった。誰も叫ばない。誰も立ち止まらない。人々は最適化された生活の中で『不便』や『違和感』を忘れ、都市の中に溶けていった。
ある夜、結城からメールが届いた。
「この都市は確かに美しい。でも、これは死んだ自然の上に建てられた美しさだよ。」
返す言葉はなかった。そして彼女は、その数ヶ月後に病でこの世を去った。
その後も都市構想は成功したと報道され、表彰もされた。俺はエンジニアとして上層部に昇進し、後輩たちに理念を語った。けれど、心の胸騒ぎが自分に語りかけてくる。
自然を排除してでも最適化することが、本当に人間らしい社会なのか?本当に生きることなのか?
答えが出たのは、その10年後──。空が完全に灰色に染まったあの日だった。
あのポスターに書かれた『持続可能』という言葉を、俺は今も忘れられない。それは、続いてほしいと願ったものではなく、壊れゆく過程を正当化するラベルだった。
かつて自分が設計した都市に、今も俺は住んでいる。この灰色の雨の中で、静かに、黙って、生きている。
風の抜ける路地を残して
都市はいま、静かに崩れかけながらも、新しい形へと生まれ変わろうとしている。
再設計の中心にいたのは、かつて構想を主導した俺自身だった。名誉はとうに失った。けれど、ようやく仕事が始まったと感じている。
都市計画局の再建チームは、驚くほど小規模だった。元エンジニアの老兵たち、環境活動家、土を触ったことのある市民。そして、ミナ──都市に育ちながら、自然を知ろうとする少女。
俺たちが最初に設計したのは、『穴』だった。
何も建てない区画。ビルを建てる代わりに、瓦礫の下から土を掘り返し、植物の種をまく。機能ゼロの広場、舗装されない路地、そして風が通り抜ける空間。それは、合理性の対極にある無駄の象徴だった。
しかし、誰もがその『風の通る路地』に足を運びはじめた。
人々はかつての都市の残骸の上に咲く小さな草に触れ、酸性雨に打たれてもなお根を張る木々の姿に驚いた。
「ここには、何もないから来たいんです」
ある若者がそう言った。都市のすべてが予定調和だった時代、人々は立ち止まる理由を持てなかった。だが、風と土と静寂があるだけの場所が、人間に余白を与えてくれた。
新しい都市設計の理念は、明文化されていない。ただ一つ、俺がチームに語り続けていることがある。
「この都市は、誰かが後悔を抱いて歩き続ける姿そのものなんだ」
都市とは、過去の選択の堆積だ。間違いがあったことを、地図に刻むこと。修復できない失敗に、木の根が食い込み、そこに草花が生えること。それを見て、子どもたちが「なんで?」と尋ね、大人たちが「昔ね」と語れる構造こそ、俺たちが築く未来だった。
ある日、ミナが広場の壁に絵を描いた。灰色の都市と、そこに咲く一本の青い花。その傍に、小さくこう書かれていた。
「きれいなまち、じゃなくて、すこし かわった まち。」
彼女は間違っていない。この都市は、二度と「きれい」にはならない。だが、変わったという歴史を抱えたまま、生きていくことはできる。
俺はふと、立ち止まり、深く息を吸った。風が、通り抜けた。
それが、設計者である俺にとっての、救いだった。
灰の隙間の青い風
この都市には、時おり旅人が訪れる。かつての『完全管理都市』が、なぜ今はこのような形にあるのか。その理由を聞くたびに、誰かが語る。
「ここにはね、たくさんのごめんねが埋まってるんだよ。でも、それを忘れないでいようって決めた街なんだ。」
風の抜ける路地に、人は集い、黙って空を見上げる。
空はまだ灰色だ。でも、時々そのすき間から、青が覗く。
それで、十分だった。
HiStory[単行本]
HiStory「シーズン1」から「シーズン4」までのお話を収録した単行本を注文できます。
完全オリジナル、完全受注生産。
ここでしか入手できない創作小説。旅のお供に持って行ったり、夜の静かな自分時間にお楽しみいただける一冊に仕上げました。
紙の本だからこその永久保存版として、ぜひあなたのライブラリーに追加してください。

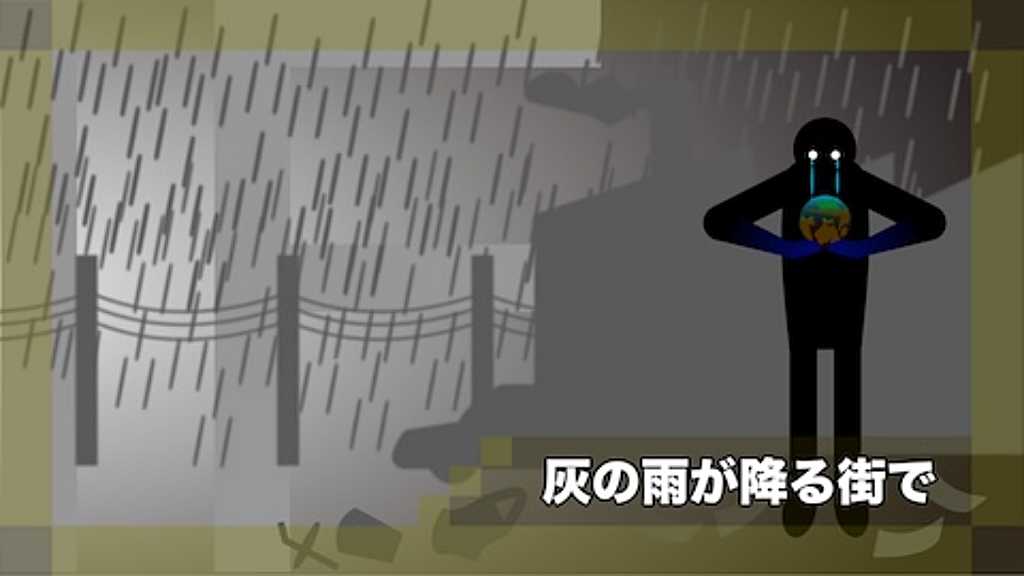
![HiStory[単行本]](https://hilens.net/wp-content/uploads/2025/07/historybook_artwork.jpg)