HiLens
写真&イラスト:デジタルクリエイティブ
日本で写真やイラストなどのデジタルアートのクリエイターをしています。
20年以上、主に鉄道の写真を撮り続けています。
これまで撮りためてきた膨大な写真を、皆様に有効活用していただきたいと思い、ストックフォトサービスを始めました。
ウェブサイト「2nd-train(旧1st-train)」への寄稿(@RSIMGS名義)
ウェブサイト「クモヤドットコム」への写真提供(@Cupmen1000名義)
ウェブサイト「First Holdings」制作
ウェブサイト「Emilys-Shop」更新支援
ポッポの丘公式サイト「クハ183-21」ページへの写真提供:2023年6月
Wikipedia画像資料提供:京成3200系電車(2代目)他
AIディープラーニング用データ提供:各種
(経歴)
交友社 鉄道ファン 2015年10月号 他
交通新聞社 鉄道時刻表情報 2008年2月号 他
富士フイルム 鉄道博物館写真展 5万人写真展:2018年7月

Camera
このカメラのおかげで私の仕事は成り立っています。小さくて丸くて可愛いのに、満足のいく写真が撮れます。とてもコンパクトなので、色々な場所に持っていきます。

Workspace
ここはHiLensの活動が行われる場所です。一見、他の部屋と同じように見えますが、私にとって一番居心地が良い場所です。一日の大半をここで過ごすので、居心地が良い空間でなければなりません。

Computer
創造力とインスピレーションをコンピューターに注ぎ込んでいます。忘れてしまう前に、どんどん速くタイピングしています。このコンテンツが皆さんにとって楽しく、楽しめるものになれば幸いです。そして今、このテキストを作成し、ここに投稿する作業に取り組んでいます。

Relux
オンとオフのバランスが大切です。リラックスできるからこそ、頑張れるんです。お風呂に入るのも大好きです。シャンプーをしている時に新しいアイデアが浮かぶことがよくあります。
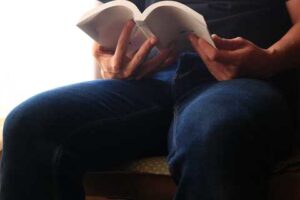
Input
満足のいく創作活動にはインプットが不可欠です。しかし、私の場合は、自分が心を動かされるものに影響を受けやすいので、インプットを厳選する必要があります。影響を受けやすいという性質を活かし、自分のコンテンツを振り返ることで方向性を修正できることに気づきました。
