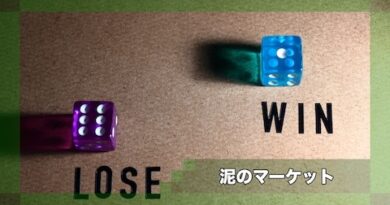レンズの先の意味 – HLHS0021

愛用のカメラとレンズ、レンズフィルター
ビルの壁に映し出された巨大な広告。そこに映るのは、AIが生成した完璧な風景。光も構図も申し分ない。「撮る」必要すらなくなった未来の都市。人々はもうスマホのカメラを構えることもない。ただ検索し、生成するだけでいい。
写真家・秋月ユウトは、その光景を見上げていた。手には使い古された一眼レフカメラ。何度も手入れをしているが、最近では街中でそれを提げて歩くだけで、まるで異物を見るような目線を浴びる。
(もう、撮る意味なんてないのかもしれない)
ユウトはそんな思いに取り憑かれていた。個展も開けず、SNSで投稿しても「AIですか?」としか聞かれない。いいねの数も、生成AI作品の足元にも及ばない。
それでも、カメラをしまえなかった。
その日、彼は郊外の古びた漁村を訪れた。取り壊しの予定があると聞いたからだ。夕暮れの海風は湿っていて、どこか懐かしい。港の片隅で、小さな少年が波を見ていた。ユウトは思わず声をかける。
「何してるの?」
「おじいちゃんの船、もう動かないんだって。でも、毎日ここに来てる。見てないと寂しくなるから」
少年の言葉に、ユウトはハッとした。
(そうか。写真も、似てるのかもしれない)
その風景が、そこに「在る」こと。それが誰かの記憶であり、愛であり、喪失であり、祈りである。ユウトはシャッターを切った。被写体はただの船ではなく、「誰かが見続けてきた風景」だった。
数日後、その写真を1枚だけSNSに投稿した。タイトルはつけず、キャプションに短くこう書いた。
「消えてしまう風景にも、見つめ続ける人がいる」
しばらく通知は鳴らなかった。けれど翌日、思いがけないメッセージが届いた。
「この船、うちの父のなんです。懐かしくて、泣いてしまいました。もう動かないけど、写真にしてくれてありがとう」
画面を見つめたまま、ユウトはゆっくりと目を閉じた。
その写真には、AIの完璧さも、演出もなかった。ただ、誰かの想いに寄り添う風景が、そこにあった。
数か月後、ユウトは小さなマガジンを作った。タイトルは『現実が、まだ美しかった頃』。全部、自分で歩き、出会い、撮った写真ばかりだった。
マガジンの巻末に、彼はこんな言葉を綴った。
「AIが世界を描けるようになった今でも、私は信じている。
光と風と、その瞬間を見つめていた“あなた”がいたことを。
写真とは、シャッターの先にいる誰かへの、手紙なのだと。」
彼の写真が突然バズることはない。でも、ページをめくった誰かの心の中で、静かに何かを灯していく。
そしてユウトは、今日もカメラを持って歩く。AIには決して写せない、「確かにそこにあった風景」を探して。
それが、自分にしかできない“表現”だと信じて。